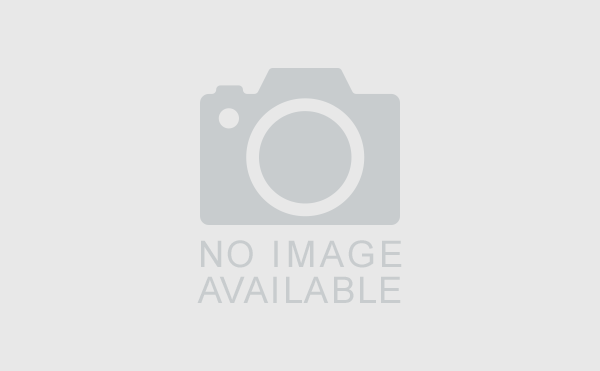〜競争を強化し、教育を財界の求める「人材」育成の道具にしようとする「第五次提言」は撤回せよ〜
【全教談話】「今後の学制等の在り方について (第五次提言)」にあたって
教育再生実行会議は、7月3日、「今後の学制等の在り方について (第五次提言)」(以下、「第五次提言」)を決定し、安倍首相に提出しました。「第五次提言」は、少子高齢化などによる「生産年齢人口の加速度的な減少」「グローバル化の進展」の中で「国力の源である人材の質と量を充実・確保」するとして、「一番のポイントは、…多様化・複線化した制度での人材教育」(2013 年 10 月 31 日第 14 回教育再生実行会議での山中文部科学事務次官)の立場で貫かれています。そのため、提言では学校制度の複線化や高校の早期卒業の制度化など競争の教育を強化するためのものとなっており、そもそも、出発点が間違っていると指摘せざるを得ません。幼児教育の無償化・義務化もこうした文脈での導入を検討しており、許されることではありません。
その第 1 は、「小中一貫教育学校(仮称)」を制度化し、諸外国にも例がない初等教育から学校制度を複線化するもので、2016 年度からの導入をめざしています。現在、各地で実施されている小中一貫教育や小中一貫校は、特区制度等を活用したものですが、制度化されれば、学校教育法等に正式に位置づけられたものとなり、教員免許や教職員定数、教科書、学校給食など関連する諸制度も改定されることとなります。
同じ学区の中に、通常の小・中学校、「小中一貫教育学校(仮称)」、「中高一貫校」などが並立し、子どもたちはいっそうの競争の中に追い込まれることになります。この結果、いじめや不登校などをいっそう深刻なものとすることが懸念されます。
もともと、文科省は 2012 年にも中教審の初中教育分科会・学校段階間の連携・接続等に関する作業部会において「義務教育学校制度(仮称)創設の是非」について検討し、「小学校入学時に選択できるのか」、「人間関係が固定化し新たに出発する機会が失われる」、「システムとしてどのような効果をもたらすのかが不明」などの反対意見も多く、中教審として導入を見送った経過があります。
そして、上記の作業部会において、「改めて検討する場合」には、小中一貫教育を推進する学校の「成果や課題等について把握、検証」した上で、「一つの学校種として『義務教育学校』を制度化することの是非、初等教育段階から学校制度が複線化することに対する考え方、…『中等教育学校』との制度的整合性等について、十分な検討を進めることが必要である」とも付言されていたものです。
こうした経過を踏まえるならば、今回の提言にあたって、少なくともこれらの検討課題が十分解明されなければならなかったにもかかわらず、教育再生実行会議において十分な解明がなされたとは言えません。この点からも中教審に諮問することは許されないものです。
第2に、こうした学制の改変を行うにあたって、「小 1 プロブレム」や「中1ギャップ」の解消をあげています。しかし、それぞれの現象の背景や要因について十分な検討や分析が行われた上での制度改定となっていないことです。
「小 1 プロブレム」については、小学校 1 年生の授業が成立しないなどの問題が指摘されています。
その背景には、入学してすぐ 5 時間授業など、現行指導要領や「学力向上」のかけ声の下での子どもたちの発達段階を無視した教育課程の押しつけの問題などがあります。また、教育再生実行会議での専門家からのヒアリングでは、少人数で丁寧にかかわることや、生活集団と学習集団が一致していることがとりわけ重要と指摘されています。このように、子どもたちの実態に応じた教育課程や学校運営の体制、少人数学級をさらに前進させることの方が重要です。
また、「中 1 ギャップ」についても国立教育政策研究所の生徒指導・進路指導研究センターが作成したリーフで「『中 1 ギャップ』という語に明確な定義はなく、その前提となっている事実認識(いじめ・不登校の急増)も客観的事実とは言い切れない」と指摘されています。
このように、今回の提言の前提そのものが成り立たないものです。
第3に、こうした学制の改変とあわせて「学校規模の適正化」の名の下に学校の統廃合もすすめようとしていることです。現在、小中一貫校の設置が特区制度等を利用して先行的に実施されている地域では、既存の学校の統廃合と一体にすすめられているところがありますが、国としてこうしたやり方を推進しようとするものです。しかも、「統廃合によって生じた財源の活用等」によって「教育環境の充実」にあてようとしていることは、ナショナルミニマムを確保する国の責任を放棄するものです。
第4に、大学などが「企業等と連携した実践的な職業教育を行うことに特化した仕組み」になっていないことなどを理由に、職業教育を行う「新たな高等教育期間の制度化」を提言しています。同時に、高等専門学校は「産業構造やグローバル化等に対応した実践的・創造的な技術者を養成」として「教育内容の改善」や「学科構成の見直し」まで提言するなど、国が教育課程の編成に介入し、教育を財界の求める人材育成の道具に仕立て上げようとするものです。
第5に、幼児教育について、「言葉の発達の早期化等を踏まえ」、幼稚園教育要領を「小学校との接続を意識」して見直し、同様に保育所や認定こども園においても見直すとしています。小学校との接続を口実に、子どもたちの発達を全面発達の視点からとらえずに、幼児教育にも「早期教育」を強化するなど、競争主義的な教育を持ち込もうとしています。
また、3歳児で 35 人学級という設置基準も改善せずに、子ども・子育て支援新制度にもとづき「制度面・財政面の環境整備」を行うとしており、問題です。
第6に、これらの学制の「改革」に対応して、複数の学校種を教えることができる免許状の創設など、教員の「免許、養成、採用、研修、配置、処遇」等制度全般の見直しをしようとしていることです。この中で「教師インターン制度(仮称)」の導入や「メリハリのある給与体系」なども提言し、教職員への管理と統制を強化するものとなっています。
第7に、「小中一貫教育学校(仮称)」の創設などとともに幼児教育の無償化など教育費負担の軽減も必要としていますが、その財源を「学校統廃合によって生じた財源」、「高齢者から子供・若者」への「資源配分」の移行、「民間資金の活用」に求めるものであり、教育費における公財政支出を GDP 比で OECD諸国並に引き上げるなどの根本的な対策となっていません。そればかりか、財源確保をめぐって国民の間に対立を持ち込むものともなりかねないものでもあります。
以上のように、「第五次提言」は、教育をいっそう競争主義的なものとし、財界の求める「人材育成」に活用しようとするものであり、断じて容認できません。全教は、こうした政策を許さず、憲法と子どもの権利条約にもとづき、子どもたちの成長・発達を保障する教育政策の確立に向けて全力をあげる決意です。